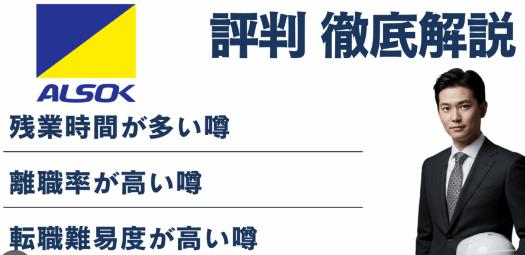警備会社のトップであるセコムですが、実際に就職・転職で採用されるのは難しいのにネットでは
- セコム就職、転職やめたほうがいい
- セコム誰でも受かる
- セコム研修厳しい
- セコム離職率が高い
・・・とのネガティブな書き込みが相当数、見受けられます
現実的に私は、呆気なくセコムの採用試験(転職)には落ちましたから・・・。
果たして、上記の情報は正しいのか?また何故そのように噂されるのか?深堀していきます
セコムは誰でも受かる
「セコムは誰でも受かる」という説は、主に以下の要因から生じていると考えられます。
慢性的な人手不足と採用の間口の広さ
-
- 24時間365日稼働の業務体制: 警備業は、顧客の安全・安心を守るという性質上、24時間365日体制でのサービス提供が不可欠です。そのため、常に多くの人員を必要とします。
-
- 未経験者歓迎の採用方針: 上記の人手不足を補うため、セコムに限らず多くの警備会社では、警備業界未経験者や異業種からの転職者を積極的に採用しています。警備業務に必要な知識やスキルは入社後の研修で習得できるとされており、学歴や職歴よりも、体力、責任感、コミュニケーション能力といった基本的な資質が重視されるため、採用の間口が広くなっていると言えます。
大規模採用と応募者の質の問題
-
- 大量採用の印象: セコムは業界最大手であり、常に大規模な採用活動を行っています。多数の採用枠があるため、一見すると「誰でも受かる」という印象を与えやすいのかもしれません。
-
- 応募者の質への誤解: ごく稀に、警備員という仕事に対して「特別なスキルが必要ない」という誤解から、安易な気持ちで応募する人がいることも事実です。そのような応募者の中には、採用基準に満たない人もいますが、それが「誰でも受かる」という言説に繋がることは、セコムの採用基準が低いという誤った認識を生む可能性があります。実際には、警備業務は人命や財産に関わる責任の重い仕事であり、一定の適性や人物像が求められます。
内定後の辞退率の考慮
-
- 採用側としては、内定を出しても辞退される可能性があるため、一定数の多めに内定を出すことがあります。これは警備業界に限らず多くの企業で行われていることですが、セコムのような大規模な会社であればその絶対数も多くなるため、「多くの人が受かっている」という印象に繋がりやすいのかもしれません。
総括すると、「誰でも受かる」というのは、セコムが多様な人材を求めており、未経験者でも積極的に採用しているという事実が、やや誇張された形で伝わってしまった結果であると考えられます。
決して採用基準が低いわけではなく、警備員としての適性や責任感を重視した選考が行われています。

セコム やめたほうがいい
「セコムはやめたほうがいい」という意見は、主に警備業界全体、そしてセコムという大企業ならではの特性に起因する、以下のような不満や課題が背景にあると考えられます。
勤務形態の厳しさ
-
- 不規則なシフト制と夜勤: 警備業の性質上、24時間365日の対応が必要なため、シフト制勤務が基本となります。特に夜勤は体力的な負担が大きく、生活リズムが不規則になりがちです。これにより、体調を崩したり、プライベートな時間との両立が難しくなったりするケースがあります。
-
- 緊急対応と待機: 機械警備の場合、異常発生時には迅速な現場急行が求められます。これは常に緊張感を伴う業務であり、待機時間中も気が抜けない精神的な負担があります。また、突発的な事態への対応で残業が発生することも少なくありません。
-
- 拘束時間の長さ: シフトによっては、勤務時間が長くなったり、休憩時間が十分に取れないと感じたりすることもあるかもしれません。特に人手不足の部署では、一人当たりの業務量が増え、拘束時間が長くなる傾向にあります。
給与水準への不満
-
- 業務内容の割に低いと感じるケース: 警備業務は、人命や財産に関わる責任の重い仕事であるにもかかわらず、基本給が他の業界に比べて高いとは言えない場合があります。特に、入社して間もない頃や、特定の地域では、給与水準に不満を感じる人もいるようです。
-
- 昇給の伸び悩み: 年功序列の傾向が残る企業においては、若手のうちは給与の伸びが緩やかだと感じる場合があります。成果が直接給与に反映されにくいと感じる人もいるかもしれません。
-
- 手当の有無と種類: 夜勤手当や残業手当は支給されますが、それが十分な額ではないと感じる、あるいは、危険手当などの特殊な手当が期待したほどではない、といった不満がある可能性もあります。
人間関係と職場の雰囲気
-
- 上下関係の厳しさ: 警備業界は、組織としての規律や指示系統が重視される傾向にあるため、上下関係が比較的厳しいと感じる人もいます。特に新入社員は、先輩や上司からの指導が厳しく感じられることがあるかもしれません。
-
- コミュニケーション不足: 警備の現場は、一人で業務を行う時間も多く、他の隊員とのコミュニケーションが希薄になりがちな部署もあります。これにより、孤立感を感じたり、困ったときに相談しにくいと感じたりするケースがあります。
-
- ハラスメントの問題(稀なケース): どの業界でもゼロではありませんが、ごく稀にパワーハラスメントなどの問題が発生する可能性も考えられます。
-
- キャリアパスへの不安
- 専門性が高まりにくいと感じる: 警備業務は、特定のスキルや経験が求められますが、それが他の業界で活かせる汎用的なスキルではないと感じ、将来のキャリアパスに不安を感じる人もいるかもしれません。
- 昇進・昇格の難しさ: 大企業であるため、昇進・昇格の競争が激しく、なかなか役職が上がらないと感じる人もいるかもしれません。
- キャリアパスへの不安
会社の規模ゆえの弊害
-
- 組織体制の硬直性: 大企業ゆえに、意思決定に時間がかかったり、新しい提案が通りにくかったりすることがあります。
-
- 転勤の可能性: 全国に拠点があるため、転勤の可能性があることも、家族を持つ人にとっては負担となる場合があります。
待遇面や人間関係の不満は、どの業界・企業でも一定数存在するものですが、警備業界特有の勤務形態が、それらの不満をより強く感じさせる要因となっていると考えられます。

セコム 研修 厳しい
「セコムの研修は厳しい」という声は、主に以下の理由から生じています。
警備業務の責任の重さと重要性
-
- 人命・財産に関わる業務: 警備業務は、お客様の生命、身体、財産を守るという極めて高い責任を伴います。万が一の事態が発生した場合、警備員の判断や行動が直接、被害の拡大や生命の危機に繋がる可能性があります。そのため、入社時に適切な知識とスキルを徹底的に身につける必要があるという認識が会社側にあります。
- 法的要件の遵守: 警備業法に基づき、警備員として従事するためには、新任教育(基本教育・業務別教育)など、一定時間以上の研修が義務付けられています。セコムはこれを厳格に遵守し、それ以上の充実した内容を提供することで、質の高い警備員を育成しようとしています。
- 人命・財産に関わる業務: 警備業務は、お客様の生命、身体、財産を守るという極めて高い責任を伴います。万が一の事態が発生した場合、警備員の判断や行動が直接、被害の拡大や生命の危機に繋がる可能性があります。そのため、入社時に適切な知識とスキルを徹底的に身につける必要があるという認識が会社側にあります。
実践的な訓練と規律の徹底
-
- 実技訓練の多さ: 研修では座学だけでなく、護身術、逮捕術、救急法、火災報知器の操作、巡回ルートの確認、緊急時の対応シミュレーションなど、実践的な実技訓練が数多く取り入れられています。これらの訓練は、実際に現場で役立つスキルを確実に習得させるため、反復練習や厳しいチェックが行われます。
-
- 規律と精神面の強化: 警備員には、冷静な判断力、迅速な行動力、そして精神的な強さが求められます。研修では、大声での点呼、整列、規律正しい行動などを徹底することで、プロ意識とチームワークを醸成し、いかなる状況下でも冷静に対処できる精神力を養うことを目的としています。これが、一部の人にとっては「厳しい」と感じられる要因となります。
-
- 体力的な要素: 上記の実技訓練に加え、巡回や緊急時の駆けつけなど、警備業務には一定の体力が必要です。研修でも、体力的な負荷を伴う訓練が含まれることがあり、これも「厳しい」と感じる一因です。

「研修が厳しい」という声は、警備業務の重要性と責任の重さを鑑みれば、当然の側面があると言えます。
むしろ、厳しい研修を通じて、現場で必要な知識、スキル、そしてプロ意識を身につけられると考えることもできます。これは、社員の安全確保、ひいてはお客様への高品質なサービス提供に繋がる重要なプロセスです。
セコム 離職率 高い
「セコムは離職率が高い」という指摘も、様々な要因が複合的に絡み合って生じていると考えられます。
警備業界全体の傾向
-
- 若年層の出入り: 警備業界は、未経験者歓迎の間口の広さから、新卒や第二新卒など、社会人経験の浅い若年層が多く入社する傾向があります。これらの層は、他の業界と比較して、キャリアに対する漠然とした不安や、早期に自分に合った仕事を見つけたいという志向が強いため、定着率が低い傾向にあります。
-
- 体力的な負担とワークライフバランス: 先述の通り、不規則なシフト制や夜勤、緊急対応など、体力的な負担やワークライフバランスの取りにくさが、離職に繋がる大きな要因です。特に、結婚や子育てといったライフステージの変化に伴い、継続が難しくなると感じる人も少なくありません。
-
- 給与・待遇への不満: 業界全体の傾向として、業務内容の責任の重さに比べて給与水準が低いと感じる人が一定数存在します。これが、より良い待遇を求めて他業種へ転職する動機となることがあります。
セコムという大企業ゆえの離職理由
-
- 組織の硬直性・風通しの悪さ: 大企業であるため、部署によっては風通しが悪く、意見が通りにくいと感じる社員もいるかもしれません。個人の裁量や自己実現の機会が少ないと感じ、退職を選ぶケースもあります。
-
- 人間関係の悩み: 組織が大きい分、様々な価値観を持つ社員がいます。人間関係の構築に悩み、それが退職の引き金となることもあります。特に、厳しい上下関係やハラスメントの存在が、一部の離職理由となる可能性も否定できません。
-
- キャリアパスの閉塞感: 警備員としてのキャリアパスに限界を感じ、他の職種や業界でスキルアップを目指したいと考える人もいます。特に、特定の専門性を深めたいと考える人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
-
- 転勤の問題: 全国転勤があるため、家族の事情や自身の居住地へのこだわりから、転勤を理由に退職を選ぶ人もいます。
入社前のイメージとのギャップ
-
- 仕事内容の理解不足: 警備員の仕事に対して、漠然としたイメージしか持たずに応募し、入社後に実際の業務内容や勤務形態とのギャップに直面して、早期に退職してしまうケースもあります。
-
- 研修の厳しさからの挫折: 前述の通り、研修が厳しいと感じ、途中で挫折してしまう人もいます。警備員としての適性や覚悟が不足していた場合、研修を乗り越えられずに退職に至ることもあります。

セコムのような大企業の場合、採用人数が非常に多いため、仮に離職率が業界平均程度であったとしても、絶対数としての離職者数が多く見えやすいという側面があります。
セコムも企業として、人材の定着には力を入れています。
福利厚生の充実、キャリアパスの多様化、労働環境の改善など、様々な取り組みを行っています。
離職率が高いと言われる背景には、上記のような複合的な要因があるものの、それが必ずしも「悪い会社」というわけではありません。
まとめ
セコムへの転職に関する不安の声について、それぞれの項目ごとに背景と実情を解説しました。
- 「セコム 誰でも受かる」
- 「セコム やめたほうがいい」
- 「セコム 研修 厳しい」
- 「セコム 離職率 高い」
これらの情報は、あくまで一般的な傾向と推測に基づいたものであり、個人の感じ方や配属される部署、支社によって大きく異なります。
就職・転職を検討される際は、これらの情報を踏まえつつ、可能であれば企業説明会に参加したり、OB・OG訪問などで現場の生の声を聞いたりするなど、ご自身で積極的に情報収集されることをお勧めします。
警備の仕事は、人々の安全と安心を守る、非常にやりがいのある仕事です。
セコムは業界のリーディングカンパニーであり、充実した教育制度や福利厚生も整備されています。
不安な点だけでなく、セコムの強みや魅力にも目を向け、ご自身のキャリアプランに合った選択をされることを願っています。